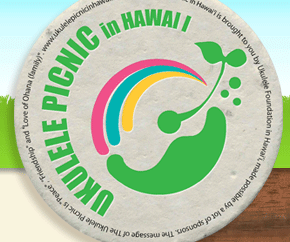|
 |
|
 |
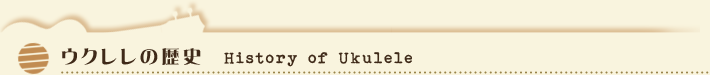 |
 |
 |
 |
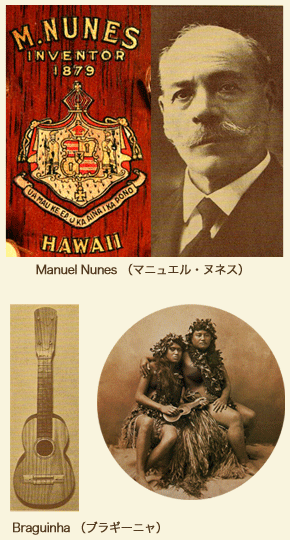 ウクレレと言えばハワイ!とすぐに思い浮かぶほど有名な楽器です。 ウクレレと言えばハワイ!とすぐに思い浮かぶほど有名な楽器です。
ウクレレはハワイの楽器。しかし、その源流は明らかにヨーロッパにある。19世紀後半、ウクレレはポルトガルからはるか海を越えてハワイにやってきた。
正確にいえば、まだその時はウクレレという名前ではなかった。当時ハワイ王国はサトウキビ畑の労働力として世界各国からの移民を受け入れていた。ポルトガルもそのひとつ。
1878年マデイラ島の港から419人のポルトガル移民を乗せて出航した船の中にはマニュエル・ヌネスとオーガスト・ディアス、ホセ・ド・エスピリト・サントという3人の職人がいた。
翌年(1879年)8月、長い航海の果てにハワイに到着した彼らはすぐに店を開き、ハワイの木材、コアを使ってブラギーニャという故郷の楽器を作り始めることにしたのだ。それが今日までハワイの楽器として親しまれているウクレレの始まりだといわれている。ウクレレ(の元になるブラギーニャ)を初めてハワイの人たちの前で披露したのもヌネスたちと同じ船に乗っていたホアオ・フェルナンデスという演奏家だといわれている。故郷の収穫祭のように、新天地への到着を神に感謝しブラギーニャを奏でみなで踊ったという。ホノルル港でそれを見ていたハワイの人たちも大喜びだったそうだ。
それぞれの職人が改良を重ね、マニュエル・ヌネスが「NUNES UKULELE」を立ち上げるなど、ハワイ独自の楽器「UKULELE(ウクレレ)」として確立して行きました。
その後、1911年にクマラエがウクレレの生産を始め、1915年のサンフランシスコで開催された「パナマ太平洋博覧会」でクマエウクレレが金賞となり、アメリカにもウクレレが渡りハワイアンブームが起きていきます。
1910年代後半からC.F.Martin社がマホガニーを使いウクレレを 生産し、市場に参入していきます。そしてハワイでは1916年にカマカ社
が設立され幾多のウクレレが生まれ、今でもすばらしいウクレレを作りだしています。
ちなみに100年後の1979年には3人の職人とブラーニャがハワイに到着した日、つまり1879年8月23日をウクレレの日と定める州政府の式典がマニュエル・ヌネスの孫に当たるレスリー・ヌネスを招き盛大に行われたという。考えてみれば不思議なことだ。おそらく太平洋の真ん中に浮かぶハワイには今までいろんな楽器が入ってきたはずだ。それこそ世界のあらゆる国から。その中でなぜウクレレがハワイに根付いたのだろう。いろんな考察は可能だ。アメリカにおけるブームも含めて、時代背景を考えると偶然に偶然が重なったこともあるだろう。しかし、重なり合う偶然はすでに必然なのだとも僕は思う。ハワイは自分たちに最も相応しい楽器を手に入れたのだと。
参考: 関口和之著 新ウクレレ大図鑑
(株)リットーミュージック2010年、13,14 pages |
|
 |
ウクレレの名前の由来
さて、ウクレレという名前はどうして付いたか、その命名にも諸説がある。
兵役を終えてハワイにやって来たイギリス軍人エドワード・パーヴィスはブラギーニャに興味を持ち、すぐにマスターした。彼はしばしば群集の前でウクレレ演奏を披露し、喝采を浴びたりしていたらしい。小柄なエドワードが演奏する姿を見た人たちが親しみをこめて「飛び跳ねる蚤」つまりUKU(蚤)、LELE(跳ぶ)と呼んだのだという説。別の解釈によると、かのホアオ・フェルナンデスの素早い指の動きが飛び跳ねる蚤を思い起こさせたという説もある。カラカウアの妹でハワイ王朝最後の女王となったリリウオカラニはもっと独創的な解釈をしていたそうだ。UKUには「贈り物」や「支払い」という意味もあったし、LELEには「やって来る」という意味もあったから「到来した贈り物」、つまりポルトガルからハワイへの贈り物、という意味なのだと。王室らしい気品のある解釈である。
前述のエドワード・パーヴィスは宮殿にもよく通っていたというから、そこでもウクレレを披露したに違いない。時のデビッド・カラカウア王はウクレレをたいそう気にに入り、イオラニ宮殿内で自らも演奏したという。当時、王は宮殿をハワイ文化の中心としようと、毎晩のようにいろいろな人を招待して晩餐会を行っていたというから、彼の奨励はウクレレにとって大きな力となったに違いない。とにかく事実として、ウクレレはハワイ諸島にやって来るやいなや、あっという間にハワイの人たちの間に広まっていったのである。 |
|
|
 |
| |
|
|
 |
|
|
 |